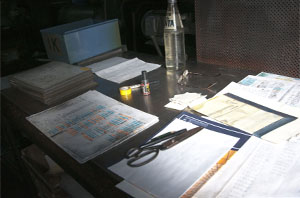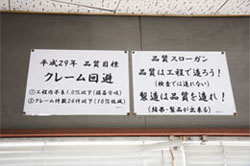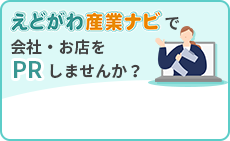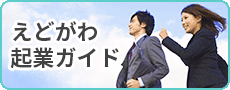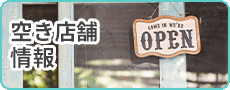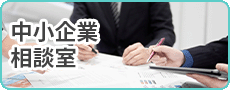平成2年に2代目として事業を継承。
「ゴムというのは『部品の部品』です。万一傷があったり不良品があったりした場合、大変なことになります。それを未然に防ぐため、様々な策を講じています。どこの会社もそうですが、見えない部分にたくさんの技術が隠されています。」
印象的な笑顔の中に、ものづくりに対する揺るぎない情熱と信念がうかがえました。
10代の頃からバイクが好きで、昔から活発的でした。
20代後半の頃に交通機動隊の隊員と意気投合したことがきっかけで、それ以来、社会貢献の思いで交通安全に尽力しています。法人会の先輩の勧めで交通安全協会にも入会、30年以上所属し、副会長を務めました。
 全国交通安全協会会長から夫婦ふたりで頂いた表彰状。
全国交通安全協会会長から夫婦ふたりで頂いた表彰状。
※2017年12月13日時点の情報です。
現在は杉井 淳様が代表取締役社長にご就任されております。

 ログイン
ログイン 新規登録
新規登録 経営応援
経営応援